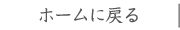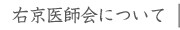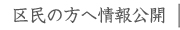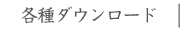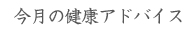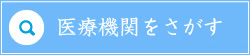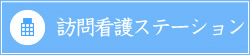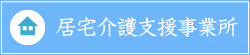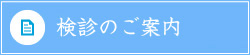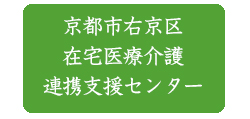ホーム > 今月の健康アドバイス > バックナンバー 2018年
![]()
2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|
2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|
12月号 「「遅寝早起き」のススメ(高齢者の方へ)」
2018年12月現在、寒くなってきており夜トイレで起きてしまうご高齢の方も多いと思います。このトイレで起きるから寝れなくなるのか、それとも良い睡眠がとれていないから起きてトイレにいってしまうのかは難しい問題なのですが、いずれにしても(それなりに眠れて)日中の活動に問題なければよいと言われています。
特にお年を召されてきた方は長く寝過ぎることも体に悪いと近年言われており、正味の睡眠時間として目安で個人差はありますが65歳なら6時間、75歳なら5時間半、85歳なら5時間でいいともいわれています。ぐっすり8時間寝れるのは中学生までです!長時間床にいる事、寝すぎる事もむしろ高血圧や糖尿病のリスクを上げるというデータもあります。冬の夜長は、布団の中が気持ちいいもの。ですが、床についている時間が長すぎるとかえって、眠りを浅くしてトイレの回数も増え、体に良くないということになってしまいます。“過ぎたるは猶及ばざるが如し”です。
一般社団法人右京医師会 伊東 晴喜
11月号 「糖尿病について」
ここ最近、テレビや雑誌などで、「医療に関する情報を目にしない日はない」といっても過言ではないと思いますが、如何でしょうか?
最新機器を使用した先進医療、アイチエイジング、介護問題など話題がつきません。今回は、もうすでに皆さんもご存知な病気とは思いますが、『糖尿病』をテーマにお話ししたいと思います。
国際糖尿病連合(IDF)の発表によると、世界の糖尿病人口は爆発的に増加しており、2017年の段階で、有病者数は4億2500万人以上と推計されており、今後も増加が予想されています。また、日本に目を向けると、厚生労働省から発表された平成28年国民健康・栄養調査では「糖尿病が強く疑われる者」は約1000万人と推計され、日本は世界でも有数の糖尿病大国であり、どなたにとっても他人事ではないかもしれません。糖尿病は、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病と、大きくは3つに分類されます。1型糖尿病は自己免疫機序により、体内からのインスリン分泌が枯渇することにより発症し、インスリン注射による治療が不可欠です。2型糖尿病は全体の約95%を占め、遺伝因子や環境因子を背景に、肥満や加齢に伴って発症します。妊娠糖尿病は、あまり馴染みがないかもしれませんが、妊娠時に初めて発症する糖尿病です。このタイプは、多くの場合、出産とともに一旦改善しますが、妊娠中にしっかり治療をしないと、胎児の臓器や成長に悪影響を及ぼすと考えられています。また一旦改善した人も、のちに2型糖尿病を発症するケースが多いと言われており、産後も定期的な検査が必要です。
これら糖尿病は、“合併症の病気”と言われており、早期に診断し、しっかり正しい治療を行わなと様々な身体的問題が出現します。かすみ目や見えにくさといった目の合併症、手足のしびれや立ち眩み、こむら返りといった神経合併症、透析に至ることもある腎臓の合併症、心筋梗塞や脳梗塞といった血管の病気、免疫力低下による肺炎や腎盂腎炎などの感染症、爪白癬などの皮膚の病気、さらには癌や認知症の発症にも糖尿病が関連していると言われています。糖尿病の初期は、症状がほとんどなく、一般的な採血検査では発見できない事もあります。職場健診や市民健診をしっかり受け、異常が指摘された場合は放置せず、必ずかかりつけ医に相談してください。11月14日はインスリンの発見日にちなみ『世界糖尿病デー』に制定されており、各地でイルミネーションやイベントが行われます。
この機会に糖尿病の方も、そうでない方も、もう一度自分の体のことを見つめ直してみては如何ですか?
一般社団法人右京医師会 池田 文彦
10月号 「風邪に抗生物質は効く?」
猛暑の夏も去り爽やかな秋になり体調も良くなる季節です。でもあと2か月もすれば嫌な風邪が流行する寒い冬となります。急な発熱やのどの痛み、咳は早く治したいですね。最近はネットで自己診断もでき、「こんな症状ならこの抗生物質が効きますよ。」などと書いてありませんか。「病院に行くのも忙しくて時間がないなー」「あ!そういえば○○先生から以前風邪のときもらっていた抗生物質があったから1錠だけ飲んでおこう。」
ちょっと待ってください。こんなふうに対応しているあなた、将来「耐性菌」にやられるかもしれませんよ。耐性菌とは肺炎などの特効薬である抗生物質が効かない菌のことです。もともと風邪のほとんどはウイルスが原因で抗生物質は効きません。そのウイルス感染に抗生物質を乱用したりすると手ごわい耐性菌が出てきます。また、最近腸内細菌の重要性もいろいろなところで聞かれると思いますが、抗生物質は腸の善玉菌も殺してしまいます。
抗生物質の歴史は細菌との「いたちごっこ」の戦いです。新しい薬が開発されるとそれに効かない菌が必ず出てきます。実は最近新しい抗生物質は開発されていないのが現状で、このままではいずれ耐性菌で亡くなる方の数が癌で亡くなる方の数を上回るとの予想もあります。
現在日本も含めて世界的に政府が主導して耐性菌対策として抗生物質の使用量を減らす計画が進んでします。抗生物質はあなたを感染症から救ってくれる大切な薬です。医師の指導のもとに適切に服用するように心がけて下さい。
一般社団法人右京医師会 竹迫 俊行
9月号 「あなたの嚥下(えんげ)機能は大丈夫ですか?」
「嚥下」とはモノを飲み込み胃に送ることを表す言葉
「嚥下障害」とはモノを上手に飲み込めない状態のことです。
一般に嚥下障害は高齢者に多いと思われがちです。しかし50歳前後から飲み込む力が少しずつ弱くなるため中高年の人なら誰にでも起こりえます。
次のようなことが増えたら嚥下障害の疑いがあります。
・食事中によくむせる
・以前はむせなかったのに時々むせるようになった(食事中でなくても)
・食べるものの嗜好が変わった(よく噛まなくてよいものを好むようになった)
・水分をとりたがらない
・食べ物がのどにちかえる感じがする
・飲み込んだ後も口の中に食べ物が残っている
・食べるとすぐに疲れて全部食べられない(体重が徐々に減ってきた)
・食後に声がかれる、ガラガラ声になる
嚥下障害になると栄養を十分に摂取できず栄養失調になったり「誤嚥性肺炎」などの病気にかかりやすくなったりするので、健康を維持するためには嚥下機能の低下を防ぐことが大切です。
自宅で簡単に行えるトレーニングをご紹介します。
1.呼吸のトレーニング 腹式呼吸(深呼吸)
口から長く息を吐きしっかり吐ききったら鼻からゆっくり息を吸い込む
2.発音のトレーニング
パ行(パ.ピ.プ.ペ.ポ)ラ行、タ行、カ行、マ行を繰り返し発音します。
3.首や口、舌のトレーニング
首のトレーニングは肩の力を抜いて首をゆっくり前後、左右に動かし首筋をしっかり伸ばすようにします。
口のトレーニングは頬を膨らましたりへこませたりを繰り返し、
舌のトレーニングは思い切り前に出したり引っ込めたりします。
回数などは自分の体力などに応じて無理のない程度にして毎日続けるようにしましょう。
訪問看護ステーション右京医師会 森岡 まゆみ
8月号 「長寿時代の健康管理」
日本人の平均寿命は戦後右肩上がりに推移して今や世界の最長寿国となりました。
2016年男性は80.98歳、女性87.14歳で香港に次ぎ世界第2位です。日本の平均寿命は1990年から2005年の15年間に劇的に伸びたと言われています。
では元々日本人の平均寿命とはどれくらいのものだったのでしょうか?
少しさかのぼって明治~大正期は44歳!(たった100年前です!)
江戸時代は30歳代(産業革命期欧米諸国も大体同じです)
奈良~戦国時代は20歳代、縄文時代は15歳と言う事です・・・これらのデータは古代については人骨よりの推定年齢、近代以降は過去帳よりの推計です。
世界的にも大体同じ傾向で、たとえば“古希”という70歳を祝うことばは唐の李白の「人生 七十 古来稀なり」(西暦757年・・日本では奈良時代)からきています。
古来長寿は王侯貴族もましてや庶民では願ってもなかなかかなえられなかったのです。
赤ちゃんや幼児が栄養や環境条件で成人するのが難しかった上、成人後も結核など感染症に全く無力な人類の歴史が何千年も続いてきました。
抗生物質が一般に使われだしたのは第2次世界大戦後です。こうしてなんとか生き残った子孫が今の私たちです
つまりこんなに長寿をみんなで経験する人類は私たちが初めてということになります。
例えば女性の生涯を考えますと、古来ずっと閉経は50歳前後です。考えてみれば人類の大半の女性は閉経を迎える前に亡くなっていたと言えます
女性は早く結婚しできるだけたくさん子供を産み育てることに忙殺されているうちに社会に出る機会もなく亡くなっていたと思われます。
日本の人口について調べると弥生時代は60万人、飛鳥~鎌倉時代は600万人、室町時代1000万人、戦国時代の終わりで1700万人、江戸時代は戦乱がなかったため2000万から3000万人に増加しました。明治維新では3300万人、その後150年で日本は異常な人口爆発を迎えピークは10年前の2008年1億2800万人に達しました。その後2009年より日本は初めて人口減少に転じ現在も人口は徐々に減少していますが問題は高齢者が増加し子供が極度に少ない人口構成です。
こうして長い歴史を俯瞰しますと現在がいかに特殊な時期であるかがお分かりになっていただけたと思います
世界的にも最高水準の医療、介護の充実で高齢者が増えましたが、一方で若い人々は子育ての環境があまりに厳しい為子供を多くもとうとしません。年々全国的に出生数が減少の一途をたどっています
このままでは有史以来の危機的状況を迎えるかもしれません。
さて私たちはなるべく存命中に健康で自立した生活を送れるように今から健康管理に気をつけましょう。現代人はオーバーカロリー、運動不足に陥りやすく生活習慣病に注意が必要です。
お近くの医療機関で高血圧、高脂血症、糖尿病の有無の確認、骨量測定(←特に女性は閉経後)、がん検診を定期的に受けられて必要な治療があればコントロールしていただきましょう。長年の人類の夢である長寿を手に入れた私たち世代はそれを大事に維持する努力が必要です。
一般社団法人右京医師会 玉置 聡子
7月号 「夏は細菌による食中毒の季節」
6月から8月にかけての高温多湿の時期は細菌が繁殖しやすく、細菌による食中毒が増加します。明らかに腐ったものを食べる人はいませんが、食べ物の色や臭いに問題がなくても、細菌が繁殖していて食中毒を起こすことが少なくありません。
また、食中毒というと飲食店での食事が原因と思われがちですが、家庭での食事でも頻繁に発生しています。
家庭での食事作りにおける食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。
≪食中毒の予防には3つの原則≫をチェックすることが大切です。
原則1. 細菌を【つけない】
・手には様々な細菌が付着しています。調理前や肉、魚を扱った後には必ず
手を洗いましょう。
・肉、魚を切った後のまな板や包丁は細菌が多く付着しています。必ず洗剤で洗った後に、他の食材に使用してください。
・菜箸は肉、魚に使うものと他の食材に使うものとで分けてください。
原則2. 細菌を【増やさない】
・食材は買って来たら、できるだけ早く冷蔵庫に入れて早めに食べましょう。
・冷凍した食品を解凍する場合は、常温での解凍は避けて、電子レンジで解凍するか冷蔵庫内で解凍しましょう。
原則3. 細菌を【やっつける】
・細菌の多くは熱に弱いので、食材を十分に加熱すれば死滅します。しっかり加熱しましょう。加熱の目安は中心部が75℃で1分以上です。
・まな板、包丁、布巾などの調理器具は洗うだけでなく、熱湯をかける等して殺菌しましょう。
自己判断せずに医療機関に
食中毒を発症すると、腹痛、下痢、嘔吐、発熱のほか、重症化すると血便なども見られ
一般社団法人右京医師会 石田 勝紀
6月号 「熱中症! 糖尿病! 劇症1型糖尿病!」
急に熱くなった日、最高気温の高い日、湿度の高い日、これから多くなりますが、熱中症には十分注意が必要です。
のどが渇く、たくさん飲む、尿の量が多い、疲れやすい、こむら返りが多い等、熱中症の症状でもあるようなそんな中に、糖尿病が隠れているかもしれません。糖尿病は、少々血糖値が高い程度では自覚症状がないことも多く、上記のような症状が出たときは糖尿病の状態が悪い、ということも多いです。
糖尿病はそもそも血糖値が高い(血液中の糖分が高い)という病態で、高血糖が続くと血管等のダメージが大きくなり、それに伴う合併症が生じ、その合併症がなかなか厄介なため、血糖値のコントロールが必要になる、病気です。3大合併症は、神経症・目の網膜症・腎症(「し・め・じ」と覚えましょう)で、しびれ、痛み、網膜症による失明、腎症による人工透析などを呈します。3大合併症以外にも、狭心症・心筋梗塞といった心臓の病気、脳出血や脳梗塞といった脳の病気、足の血管がつまるなどの末梢動脈の病気、も多くなります。
糖尿病にも種類があり、大きくわけて、1型、2型、妊娠糖尿病、その他、に分けられますが、一般的に大人がなる糖尿病は2型です。肥満等により血糖値を下げるホルモンであるインスリンが、体の中でうまく作用しなくなったり、インスリン分泌が低下したりして血糖が上がる病態です。それに対し1型は膵臓から分泌されるべきインスリンそのものが産生されない病態です。この1型糖尿病の中で注意すべき糖尿病として、劇症1型糖尿病という病気があります。短期間に糖尿病を発症し適切な治療を開始しないと死に至ることもある危険な病気です。基本的にのどが渇く・たくさん飲むなどの高血糖に伴う症状はあまりなく、急に意識がおかしくなって病院を受診するといったこともあります。インスリンが分泌されていないため体内の糖分が使われず脂肪を利用するため、ケトン体という物質が産生され、結果、血液が酸性となり昏睡状態になる、危険な病態です。一般的な1型糖尿病が若い時に発症するのに対しこの劇症型は、平均して男性43歳、女性35歳に発症すること、男女比は1対1で日本を含め東南アジアに多いといったデータがあります。典型的な糖尿病の症状が少なくいきなり昏睡になることもあり、気を付けるべき糖尿病です。
熱中症と思われる中にも、糖尿病が隠れているかもしれず、いつもと違う、何かおかしい、といったことがあれば医療機関を受診するように、お願いいたします。
一般社団法人右京医師会 寺村 和久
5月号 「帯状疱疹のワクチン接種が始まりました」
みなさん、右京医師会のホームページにようこそ!このコーナーは右京医師会の会員が市民の皆様方に健康に関するアドバイスをするコーナーです。様々な科の医師がタイムリーで有益な情報を発信しています。今月は、帯状疱疹の予防接種についてお知らせしたいと思います。帯状疱疹の原因は、みずぼうそうのウィルスと同じです。子供の頃にかかったみずぼうそうが治ったあと、知覚神経の細胞の中にウィルスが潜伏感染します。その後、何十年も症状がないのですが、ストレス、疲労や老化などにより免疫が低下し、ウィルスが再び神経の中からどんどん複製し、神経線維をたどり、皮膚に水ぶくれをつくる病気です。何より問題になるのは、神経での炎症による痛みで、それが残ることです。ウィルスをおさえる薬はあるのですが、このやっかいな神経痛を完全におさえる薬はいまだ開発されていません。ですから、発症そのものをおさえるワクチンが有効ということになります。実はこの帯状疱疹は、子供のみずぼうそうのワクチンが定期接種化されてから増えています。というのも巷でのみずぼうそうの流行が減り、定期的に生ウィルスに暴露される機会が減ったことが原因と言われています。とくに50歳以上での帯状疱疹の発症が増えています。この辛い神経痛を予防するには、予防接種が一番よい解決策ということになります。今のところ、この予防接種は自費での接種となります。また、すべての方が適応となるわけではありません。くわしくはかかりつけ医や皮膚科医などにご相談下さい。
一般社団法人右京医師会 松木 正人
4月号 「学童期のからだの痛み、なぜ治らないのか? 」
子供さんの体の痛みは捻挫や打撲といった外傷の場合、受傷機転ははっきりしています。一方、ずっと運動を継続している学童でいつのまにか痛みを生じて運動ができないといった症状でこられる子供さんも多くおられます。身体の老化に無縁な時期である成長期のこどもさんになぜ痛みが? 詳しく話を聞くと大人なら動けなくなるだろうとおもわれるほどの運動量をこなしている子供も多いです。発達曲線によると小学6年~中学1年では運動器骨格の成長は成人の40%-50%程度です。90%以上とほぼ同等になってくるのは高校2年生くらいからですので、この時期おこりやすいのは運動の過負荷により壊れたとおもわれる症状です。これらの痛みは発症初期の状態で適切な運動中止と復帰の指導があればほとんどが治癒します。子供の運動したい希望ありスポーツを中止できないという保護者も多いですが、将来のために「子供の体をまもる」意識が必要です。学校生活や家庭環境に問題のある場合もあるため神経科、心療内科との連携が必要になることもあります。子供の体の痛みにたいしては安易に考えずに整形外科専門医に受診をするようお願いします。
一般社団法人右京医師会 小室 元
3月号 「いつもよく風邪をひく・よく咳が出る
そんなときはアレルギーの可能性を考えましょう 」
「いつも風邪ばかりひいているんです。なんだか調子が悪くて。」「そうですか。いつも鼻水が出るんですか?」「そうなんです。鼻水が出たかと思うとすぐに調子が悪くなって喉が痛くなって・・・。」外来での患者さんとの会話です。この患者さんの場合、採血の結果、ダニ・ダストアレルギーが判明しました。
風邪だとおもっていたが実は、アレルギー性鼻炎・咳喘息をもっていて、その結果、ばい菌にも弱くなり副鼻腔炎を起こしてしまう、扁桃腺炎を起こしてしまう、ということはよくあります。つまり、見た目は風邪だけれど、裏にはアレルギーが潜んでいるのです。
ダニ・ダストアレルギーを例にあげますと、布団・毛布をこまめに洗濯できるものに変える、長年万年床なら一回買い換えるなど、生活習慣に即した方法も効果がありますし、現在は、ダニ舌下療法といって、ダニの成分を舌の下に2分間保持して、ダニに対してのからだのアレルギー反応を起こしにくくするといった治療法もあります。
アレルギーの患者さんにとって大事なことは、「扁桃腺炎や副鼻腔炎になってひどい風邪を繰り返さないように、予防薬やアレルゲンの除去の努力、舌下療法などによって、アレルギーをひどくしないこと」なのです。
「風邪ばっかり繰り返しているなあ」と思っている方は、ぜひ、アレルギーの検査をしてみましょう。
一般社団法人右京医師会 紀 優子
2月号 「肺炎の予防注射を受けましょう」
京都市では平成26年度から平成30年度まで高齢者に成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種が行われております。とは言え経過措置で、対象者は今まで同ワクチンを接種したことがない方で、年齢がその年度内に65・70・75・80・85・90・95・100才になる京都市民と、60~64才になる京都市民で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に障害を生じている方のみです。
抗生剤の進歩により肺炎は容易に治療できる過去の疾患と考えていませんか。高齢者の肺炎は治りにくく、一旦治っても肺炎を繰り返したり、身体が弱って寝たきり状態になることがしばしばで、認知症の発症リスクも上がります。また高齢になると飲み込む力(嚥下機能)と誤嚥したものを喀出する力が弱くなり誤嚥性肺炎を起こし易くなります。高齢者に多い誤嚥性肺炎の原因菌は口腔内常在菌である肺炎球菌であることが多いです。この肺炎球菌による肺炎の予防には肺炎球菌ワクチンが有効です。定期接種の対象者には自治体からの案内が郵送されておりますが、当該年度の3月末までですので、これを逃すと4年後の4月1日まで自治体からの補助を受けられません。その上、現在の方法は平成31年3月31日までの経過措置ですので、それ以降にどうなるのかはわかりません。高齢者、中でも成人用肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者の方々は、肺炎なんか関係ないよ、と思わずに予防注射を受けられることをお勧めします。料金は4000円ですが、自己負担区分証明書の提出により市・府民税非課税者は2000円、生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者は無料となります。定期接種でない場合は全額自己負担で8000円程かかります。なお、今回のワクチンは23価ワクチンで一生に一回の接種ですが、接種後5年ほどでその効果が落ちることから自己負担にはなりますが同ワクチンの再接種とプレベナーという名の13価ワクチンの追加接種が望ましいです。
一般社団法人右京医師会 岩田 弘滋
1月号 「補聴器を正しく使いましょう」
我が国は欧米に比べて補聴器を使用する方の割合がかなり低いとのことです。難聴は恥ずかしいので知られたくないという文化によるものかと思われます。しかしながらそれによって会話を聞き間違えることが多くなり、人との接触が億劫(おっくう)になるなどの損失の方がはるかに大きいのではないでしょうか。コミュニケーションの減少から加齢による難聴で認知症発症のリスクが増大し、適切に補聴器を使用することでリスクを軽減できるとのデータもあります。最近は補聴器性能の向上とともに小型化も進み、装用していてもあまり目立たなくなっています。流行りの音楽プレーヤーのように颯爽(さっそう)と使用している方もお見受けします。とはいえ補聴器の普及を妨げてきた責任の一端は、その使用を適切に推奨・指導してこなかった私たち耳鼻咽喉科医にもあります。
そんな反省を踏まえ日本耳鼻咽喉科学会では「補聴器相談医」制度を運用しており、制度のあらましや相談医の名簿については学会ホームページ(http://www.jibika.or.jp/citizens/)で確認できます。難聴の程度や補聴器使用の必要性などについては一人一人異なります。したがっていきなり通販での購入などは論外です。ご家族に難聴の方がおられて補聴器のプレゼントをお考えの方もまずはご本人同伴で耳鼻咽喉科への受診をお勧めいたします。認定された補聴器専門店と連携して適切な補聴器の選択をお手伝いいたします。なお、補聴器は医療保険の適応外ですが、使用が不可欠な高度難聴については公的補助の制度もございますので併せてご相談ください。
一般社団法人 右京医師会 寺薗 富朗